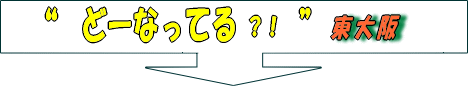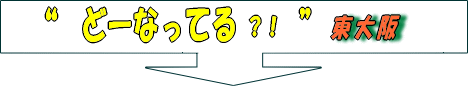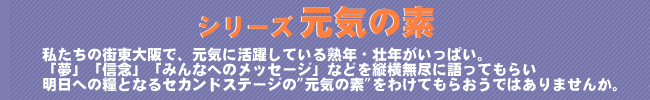 |
ƒCƒ“ƒ^ƒrƒ…پ[پ@‚»‚ج‡X |
| پg‚ـ‚à‚ب‚•ؤژُ‚جƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒA‚³‚ٌپh |
| •g“c‚©‚¸‚ï ‚³‚ٌ |
پ@‚à‚¤‚·‚®•ؤژُ‚ئ‚ب‚éڈ—گ«‚ھچ،‚àƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒAٹˆ“®‚جŒ»–ًپIژg‚¢‚±‚ٌ‚¾ˆ¤—p‚ج“d“®ƒ~ƒVƒ“‚ًƒtƒ‹‰ز“®‚³‚¹‚ب‚ھ‚çپAکVگl‰ïپE“ء—{ƒzپ[ƒ€پE—c’t‰€پE•غˆçڈٹ‚ب‚ا‚ةڈo‚©‚¯پA‚ف‚ٌ‚ب‚ةŒ³‹C‚ً•ھ‚¯—^‚¦‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB
پ@‚»‚جŒ³‹C‚جژه‚حپAژلچ]“Œ’¬چفڈZ‚ج•g“c‚©‚¸‚ïپi‚ذ‚邽پE‚©‚¸‚¦پj‚³‚ٌپB‚W‚Vچخ‚إ‚·پB
‚ـ‚ي‚è‚ةگ¢کb‚ً‚µ‚ؤ‚à‚ç‚ء‚ؤ‚¨‚©‚µ‚‚ب‚¢”N—î‚ب‚ج‚ةپAگl‚ج‚¨گ¢کb‚ً‚·‚鑤‚ةپB‚ف‚ب‚³‚ٌ‚ح‚»‚ٌ‚بژ©•ھ‚جژp‚ًژv‚¢•‚‚©‚ׂç‚ê‚ـ‚·‚©پH•g“c‚³‚ٌ‚جŒ³‹C‚ج‘f‚ة”—‚è‚ـ‚·پB |
 ‚V‚Tچخ‚²‚ë‚©‚çƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒAٹˆ“®‚ضپI ‚V‚Tچخ‚²‚ë‚©‚çƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒAٹˆ“®‚ضپI |
پ@‚©‚¸‚‚ٌ‚حپA‚P‚X‚R‚T”Nپiڈ؛کa‚P‚O”Nپj‚ة–¼Œأ‰®‚©‚çڈW’cڈAگE‚إ‘هچم‚ةڈo‚ؤ‚«‚ـ‚µ‚½پBڈم–{’¬‚جٹwگ¶–X‚ج–Dگ»چHڈê‚ةڈAگE‚µپAگ””NŒم‚ةژلچ]‚جچHڈê‚ةˆع‚è‚ـ‚µ‚½پB“–ژ‚جگ¢ٹE‚ح“®—گ‚جچإ’†پB“ْ–{‚à“ْ’†گي‘ˆ‚©‚ç–{ٹi“I‚ب‘و“ٌژں‘هگي‚ض‚ئ“Dڈہ‚ة‚ح‚ـ‚肱‚ٌ‚إ‚¢‚ژ‘م‚إ‚·پB‚©‚¸‚‚ٌ‚ح•؛‘à‚ھ‘«‚ة‚ـ‚ƒQپ[ƒgƒ‹‚â–Xژq‚جƒ~ƒVƒ“ٹ|‚¯‚جژdژ–‚ةگ¸‚ًڈo‚µ‚½‚ئ‚¢‚¢‚ـ‚·پB‚»‚êˆب—ˆپA–Dگ»‚جژdژ–‚ذ‚ئ‚·‚¶‚إ‚µ‚½پB
پ@‚P‚Q”N‘O‚ة•v‚ھ–S‚‚ب‚è‚ـ‚µ‚½‚ھپA‚Q”Nٹش‚ح•v‚ج‰îŒى‚ة‘S—ح‚ً‚©‚½‚ق‚¯‚ـ‚µ‚½پB•v‚ًٹإژو‚ء‚ؤ‚©‚çپA‚©‚¸‚‚ٌ‚جƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒAٹˆ“®‚ھژn‚ـ‚è‚ـ‚µ‚½پB‚©‚¸‚‚ٌ‚V‚Tچخ‚ج‚±‚ë‚إ‚·پB‚±‚ج”N—î‚©‚çƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒAٹˆ“®‚ئ‚حپAگg‘ج‚ھڈن•v‚إچھ‚ء‚©‚ç‚ج“‚«ژز‚ج‚و‚¤‚إ‚·پB
پu‚¶‚ء‚ئ‚µ‚ؤ‚ç‚ê‚ض‚ٌگ«•ھ‚₳‚©‚¢گg‘ج“®‚©‚µ‚ؤ‰½‚©‚µ‚ؤ‚ض‚ٌ‚ئپA“ْ‚ھ•é‚ê‚ٌپvپuگج‚©‚çگg‘ج‚ھ‚»‚¤‚ب‚ء‚ؤ‚ٌ‚ث‚ٌ‚ث‚¦پv‚ئ‚ح–{گl‚ج•ظپB‚آ‚â‚آ‚â‚جٹç‚ً‚ظ‚±‚ë‚خ‚ب‚ھ‚çŒê‚è‚ـ‚·پB |
 |
| •g“c‚©‚¸‚ï ‚³‚ٌ |
|
|
 ‘K‘¾Œغ‚جژè—x‚è‚ح‚ف‚²‚ئ ‘K‘¾Œغ‚جژè—x‚è‚ح‚ف‚²‚ئ |
| پ@‚©‚¸‚‚ٌ‚جٹˆ“®‚ج’†گS‚حپAپu‘K‘¾Œغپv‚ًژg‚ء‚½ژè—x‚è‚ً•پ‹y‚·‚邱‚ئپBژlڈً‚ج‰ئ‚â“ء—{کVگlƒzپ[ƒ€پA—c’t‰€پAŒِ–¯ٹظٹˆ“®‚ب‚ا‚إپAژ©گg‚ھژè—x‚è‚ً”âکI‚µپAژèچى‚è‚جپu‘K‘¾Œغپv‚ًƒvƒŒƒ[ƒ“ƒg‚µ‚ؤپA‚ف‚ٌ‚ب‚إٹy‚µ‚ف‚ـ‚·پB |
 |
پ@پu‚ذ‚ئژRپA‚س‚½ژRپAژOژR‰z‚¦پEپEپEپv‚ئ‹ب‚ة‚ ‚ي‚¹پA‘K‘¾Œغ‚ً—¼ژè‚ةژ‚ء‚ؤپA•G‚âڈ°‚ًŒy‚‚ئ‚ٌ‚ئ‚ٌپBڈم‰؛چ¶‰E‚ةƒٹƒYƒ€‚ً‚آ‚¯‚ؤگU‚é‚ئپA‚µ‚ل‚ٌ‚µ‚ل‚ٌ‚ئ‚¢‚¢‰¹گFپBƒoƒgƒ“ƒgƒڈƒ‰پ[‚ج‚و‚¤‚ة’ˆ‚ة‚‚é‚ء‚ئ‰ٌ‚µ‚ؤژ‚؟‘ض‚¦‚½‚èپAŒًچ·‚³‚¹‚½‚è‚ئŒy‰ُ‚ةŒ©‚¦‚ـ‚·پB‚µ‚©‚µپAچ¶‰E‚جژè‚ج“®‚«‚ھˆل‚¤‚ج‚إپA“¯ژ‚ة‘€‚é‚ج‚حژٹ“ï‚ج‹Z‚إ‚·پB
پ@‚©‚¸‚‚ٌ‚حژ茳‚àŒ©‚¸پAڈخٹç‚إٹy‚µ‚»‚¤‚ة‚â‚ء‚ؤ‚‚ê‚ـ‚·پB“ْپX‚جگد‚فڈd‚ث‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB |
|
پ@پ@ چل‚¦‚éƒ~ƒVƒ“‚ج‹Z چل‚¦‚éƒ~ƒVƒ“‚ج‹Z |
| پ@‚©‚¸‚‚ٌ‚جپu‘K‘¾Œغپv‚حپAƒ‰ƒbƒv‚جژ†“›‚ًگc‚ة‚µ‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚»‚ج’†‚ة‚حڈ¬“¤پE—éپEŒـ‰~‹ت‚ئ‚¢‚ء‚½‚à‚ج‚ھ“ü‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚»‚ê‚ة‚«‚ê‚¢‚ب•z‚ً‚©‚¯پA—¼’[‚ًچi‚ء‚ؤ‚ ‚è‚ـ‚·پB—¼’[‚ة‚س‚³‚âƒ{ƒ^ƒ“‚جƒAƒNƒZƒ“ƒg‚ھ‚آ‚¢‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBگج‚ئ‚ء‚½‚«‚ث‚أ‚©‚إپAˆ¤—p‚ج“d“®ƒ~ƒVƒ“‚ھٹˆ–ô‚µ‚ـ‚·پB‚©‚¸‚‚ٌ‚ج‹Z‚ھچل‚¦“n‚èپA•z‚حƒsƒVƒb‚ئŒˆ‚ـ‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پB‚à‚ئ‚à‚ئپu‘K‘¾Œغپv‚ح–¯‘°ٹyٹي‚جˆê‚آپBڈ¬‘¾Œغ‚ج‚س‚؟‚ةڈ¬‘K‚ً‚آ‚¯‚ؤƒ^ƒ“ƒoƒٹƒ“‚ج‚و‚¤‚ة‘إ‚آƒ^ƒCƒv‚ئپA’|“›‚ة“؛‘K‚ب‚ا‚ً‚¢‚ê‚ؤ‚»‚ê‚ً‘إ‚؟–آ‚ç‚·ƒ^ƒCƒv‚ھ‚ ‚è‚ـ‚·پB‚©‚¸‚‚ٌ‚حپA“‡چھŒ§‚ج’|“›ƒ^ƒCƒv‚ًژQچl‚ة‚µ‚½‚»‚¤‚إ‚·پB‚©‚¸‚‚ٌ‚جچى•i‚حپA–¯Œ|•i‚ة‚à‚ذ‚¯‚ً‚ئ‚ç‚ب‚¢‚·‚خ‚炵‚¢ڈo—ˆڈم‚ھ‚è‚إ‚·پB |
 |
| ‚¨ژèگ»‚ج‘K‘¾Œغ‚ئ‚¨ژè‹ت |
|
 |
| ’·”Nˆ¤—p‚ج“d“®ƒ~ƒVƒ“ |
|
|
| پ@ٹeژ{گف‚ة‚حپA‘K‘¾Œغ‚ج‚ظ‚©پA‚¨ژè‹ت‚àچى‚ء‚ؤ‘،‚è‚ـ‚·پB‘K‘¾Œغ‚ئ‚¢‚¢پA‚¨ژè‹ت‚ئ‚¢‚¢پAژw‚ئژè‚ًژg‚¢پAڈم”¼گg‚ج“K“x‚ب‰^“®‚ة‚ب‚é‚ج‚إپA‚¨”Nٹٌ‚è‚ج‹@”\‰ٌ•œ‚¾‚¯‚إ‚ب‚پA—c‚¢ژq‚ا‚à‚½‚؟‚ة‚حپA—ا‚¢‚¨‚à‚؟‚ل‚ئ‚ب‚è‚ـ‚·پB‚©‚¸‚‚ٌ‚ة‚ئ‚ء‚ؤ‚àپAژèچى‹ئپEژè—x‚èپEƒٹƒYƒ€‰^“®‚حŒ³‹C‚ج”éŒچ‚©‚à‚µ‚ê‚ـ‚¹‚ٌپB |
پ@ ژل‚¢‹Cژ‚؟‚ئپAٹى‚ر‚ً‹¤ٹ´‚·‚éگS ژل‚¢‹Cژ‚؟‚ئپAٹى‚ر‚ً‹¤ٹ´‚·‚éگS
|
پ@‚©‚¸‚‚ٌ‚ج‰ئ‚حپA‹كڈٹ‚جگl‚½‚؟‚جٹٌ‚èچ‡‚¢ڈê‚ة‚ب‚ء‚ؤ‚¢‚ـ‚·پBƒnƒڈƒCƒAƒ“ƒhƒŒƒX‚إƒtƒ‰ƒ_ƒ“ƒX‚ً—x‚邱‚ئ‚àپB‚س‚ئŒ©‚é‚ئپAگ®—ƒ_ƒ“ƒX‚جڈم‚ة‚ح‘هگ³‹ص‚ھپEپEپEپBپu‚±‚ê‚à‚â‚ء‚ؤ‚¨‚ç‚ê‚é‚ج‚إ‚·‚©پv‚ئ‚¢‚¤–â‚¢‚©‚¯‚ةپAپu‚½‚ـ‚ة‚â‚è‚ـ‚·پv‚ئ‚ج•شژ–پB‰½‚ة‚إ‚à’§گي‚·‚éژل‚³‚ًٹ´‚¶‚ـ‚·پB
پ@ڈT‚ة‚Q“x—ˆ‚éƒwƒ‹ƒpپ[‚³‚ٌ‚حپu‚©‚¦‚ء‚ؤŒ³‹C‚ً‚à‚炤پv‚ئŒê‚ء‚ؤ‚¢‚é‚ج‚à‚¤‚ب‚¸‚¯‚ـ‚·پB |
 |
ƒsƒ“ƒN‚حژ—چ‡‚¤‚©‚ب‚ئ
ڈ‚µ‚ح‚ة‚©‚ق‚©‚¸‚‚ٌ‚ئ
پ@–؛‚جٹى”üژq‚³‚ٌ |
|
 |
‘هگ³‹ص‚ة‚à’§گي
|
|
|
|
ژوچق‚ًڈI‚¦‚ؤ
پ@‚ف‚ب‚³‚ٌپA‚V‚Oچخ‚â‚W‚Oچخ‚جژ©•ھ‚ھ‚©‚‚µ‚ل‚‚ئ‚µ‚ؤƒ{ƒ‰ƒ“ƒeƒBƒA‚ً‚µ‚ؤ‚¢‚éژp‚ً‘z‘œ‚إ‚«‚½‚إ‚µ‚ه‚¤‚©پB
“ْچ ‚©‚烉ƒbƒv‚جگc‚₨ژè‹ت‚ج‚ح‚¬‚ê‚ً‚ ‚؟‚±‚؟‚©‚çڈW‚كپA‚ف‚ٌ‚ب‚ةƒvƒŒƒ[ƒ“ƒg‚·‚邽‚ك‚ة‚¹‚ء‚¹‚ئƒ~ƒVƒ“‚ةŒü‚©‚¤‚©‚¸‚‚ٌپB‚©‚¸‚‚ٌ‚جگS‚ة‚حٹى‚ش‚ف‚ٌ‚ب‚جٹç‚ھ•‚‚©‚ٌ‚إ‚¢‚é‚و‚¤‚إ‚·پBگl‚جٹى‚ر‚ًژ©•ھ‚جٹى‚ر‚ة‚إ‚«‚éگ¶‚«•û‚ةٹ´–ء‚ًٹo‚¦‚ـ‚·پB
•”‰®‚ج•ا‚ة‚حپu‰ْکVک^پv‚ھ“\‚ء‚ؤ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½پBپu‚µ‚ؤ‚à‚炤‚ج‚ح“–‘R‚ئژv‚ي‚ت‚±‚ئپvپuٹى‚ر‚ً—^‚¦‚邱‚ئپv‚ئ‚ ‚è‚ـ‚µ‚½‚ھپAŒ¾—t‚ج‰ْ‚ك‚و‚è‚àپA‚©‚¸‚‚ٌ‚ج‘¶چف‚»‚ج‚à‚ج‚ھژü‚è‚جگlپX‚ةٹى‚ر‚ئŒ³‹C‚ً—^‚¦‘±‚¯‚ؤ‚¢‚é‚و‚¤‚إ‚·پB
پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@پ@–ىŒûپ@’تگMˆُ |
|
|