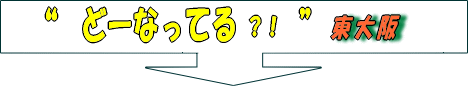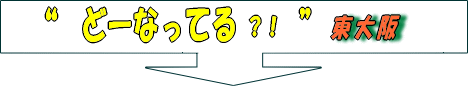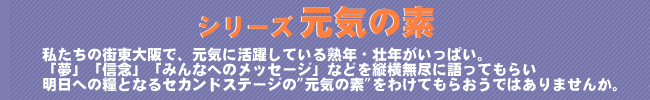 |
| �C���^�r���[�@���̇\ |
���`���̎�Â���l�`���@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��������q����
�@�����ɓ��{�l�`������L���ȍH�[������̂������m�ł����H
�s���r��P���ڂɂ����l�`�H�[�w�����i���傤����j�x������B
���F�́u�ߋ�l�`�H�|�m�v�́A�S���łV�O�l�������܂��A��
���ɂ͂S�l���ݐЂ��Ă��܂��B�@���̂����̈�l�ŁA�H�[�ɒ��N��
�����A�W�O���錻�݂ł��A�Ȃ��������Ⴍ�Ƃ��Đl�`����
��ޏ��������܂��B���C�Ȑ���������w�т����B
�@ |

|

|
 �@������ �@������
�@�@�@�@�u�ߋ�l�`�H�|�m�v
�@�l�`�H�[�w�����x�̃X�^�b�t
�̈�l�ł����������q����
�i�W�R�j�́A�����́u�ߋ�l
�`�H�|�m�v�ł��B
�@�T�ɂT���A���]�ԂłP�T����
�ǂ̎����ʂ��A����ɂT��
�ԂقǍH�[�Ŏd��������Ă�
�܂��B�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
�@�@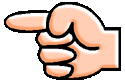 �@ �@ |
|
 �@�u���R�l�`�v�ɐS���𒍂� �@�u���R�l�`�v�ɐS���𒍂�
�@
�@�W���R�[�i�[�̈�p�ɂ����
�ƕ��ׂ��Ă���̂́A�]�ˏ�
���L���ȁw���R�i����܁j�l�`�x�B
�@���䂳��̎�ɂȂ���̂ŁA��
���Ƃ����ӂƂ��镪��ł��B����
�̃f�U�C���A�z�n�╿�̑g�ݍ�
�킹�ȂǁA�����̖L����������
�Ȃ��A�a���ɑ��鑢�w�̐[����
�K�v�ƂȂ�܂��B
���R�l�`�F���t�̗R���ɂ͏�������B�]��
�@�@�@�@�@�@�����̑�l�̏����̐l�`�B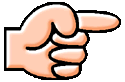 |
�@ |
|

�@�@�@�@�@�@�@�������q����
|
 �ÓT���w�E�|�\�ɒ^�M�̖����� �ÓT���w�E�|�\�ɒ^�M�̖�����
�@�c�����납�當�w�ɖڊo�߂܂����B
�펞���A�Z�܂��̐����̖h��
���ɖ{��������A���{�����S�W����
��ł����Ƃ����܂��B��P�x��
��ƁA�Ȃ��킭�킭���Ėh��
�ɂނ����܂����B�����������Ǝ���
�Ƀi�x�������A�����u��ۂ�ۂ��
�ɂق���Ȃ���{�̐��E�ɐZ����
���Ƃ��B
�@�c�Ɍ����A���ƕ���A���߁A�ߏ�
����ǂ��Ƃ��A�̂��ɉ̕����
���y�̕���ɋ��������f�n�ƂȂ�
�܂����B
�@���̕���Ƃ̏o��́A�w���R
�l�`�x�������ŁA�M�d�Ȍo����
�Ȃ��Ă���悤�ł��B
|
|
�@�@�@�@�@ �@���w�����x�Ƃ̏o� �@���w�����x�Ƃ̏o�
�@���݂̐l�`�H�[�̎�Ɏ҂́A�u�ߋ�l
�`�H�|�m�v�œ��ځw�����x�����o�N�Y
�����B�w�����悵�l�`�x�̎В�����ł�
����܂��B
�@����w�����x�́A��e�����o�������B
�@���A���䂳��͑��̕���̖��͂�
�͂܂�A��Őj����z���W�߂āA����
���s�������u������l�`�v�����n��
�܂����B���̌�A����w�����x�Əo�
�A�H�[�œ������ƂɂȂ�܂��B�ȗ��A��
�R�l�`�A�����W�A�A���q�Ȃǂ��肪��
�邱�ƂɁB
�@���䂳��́u�{���ɐl�`���D���ł���
����A���ꂪ���d���Ɍ��т��č���
�܂ŗ����čK���Ȏ��ł��v�ƌ��܂��B
�@���ځw�����x�̍N�Y����́A�����
���䂳����������Ȃ���A�˔\������
�ł���悤�C��z���Ă��܂��B
������l�`�F�킪���̉����A�����ɑ�ނ��Ƃ�A�t�����X
�@�@�@�l�`�̐���@�ɂȂ���đS�̂��z�ō��ꂽ����
�@�@�@�̑��́B
|

�@���ځw�����x���o�N�Y���� |
|
|
|
|
|
 �@�D��S�������ς� �@�D��S�������ς�
�@�u���i�Ƃ��ė����x�������Ă͂Ȃ�Ȃ��v
�ƁA�o���オ�肪�C�ɓ���Ȃ����̂́A��
���Ĉꂩ���蒼���Ƃ������䂳��B
�@�c��������l�`������ĐQ�Ă��������́A
�����A��e�A�E�ƕw�l�ƕ��݂Ȃ���A���|��
���ɂ����������������Ă��܂����B
�@���́A���q�̂��ł���̐��b�ɂȂ炸�A��
�l��炵���y����ł��܂��B
�@�Ï��X�ɔ�э���ʼnC�������w�̑�햡��
�킭�킭������A�e���r�̉̕���ԑg�����X��
�^�悵���肵�Ă��܂��B�����E�̌o������A�p
�\�R���������܂��B�@�]�˂̐��A�l��A�����A
�����Ă��̔������ɖ�����A�u����ɋ߂Â���
�߂ɂ́A���ł�����Ă݂����v�ƁA�D��S��
���ς��̏����̂悤�ȕ��䂳��ł��B
|

�@�S�O�N�قǑO�A���s����
�����u������l�`�v���A��
�悤���܂˂ō�����B |
|
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@
 |
�@�D���Ȏ��ɑł�����ŗ���ꂽ
���䂳��B�Ƃ͂����A�h�����Ƃ���
�������Ƃ�����������z���Ă���
�ꂽ�ɂ������Ȃ��B���ł͓V�E��
�Ȃ����l�`���B�L���Ȋ����ŁA
���炵�����̂����葱���Ă���
���������B
�@���悵�l�`�̓X�܂ɂ́A���l�`
�A�s���l�`�A���R�l�`�A�ؖڍ���
�l�`�Ȃǂ�������̎�ނ̐l�`��
�o�ׂ�҂��Ă����B
�@���ł��A�a�V�ȃf�U�C���̗���
���ڂ��Ђ����B�i���̎ʐ^�j�@�X��
���t�X�L�[�Ƃ����N���X�^���K���X
���T�V�O�O�قǂ���߂��V���i
���Ƃ����B�`���ɐV�����A�C�f�A��
�������l�`�H�[�̋C�T���������B�@http://www.koubou-shouju.com�@�l�`�H�[�@�w�����x
|
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@���|�[�g�F������� |
| �@ |
|
|